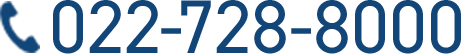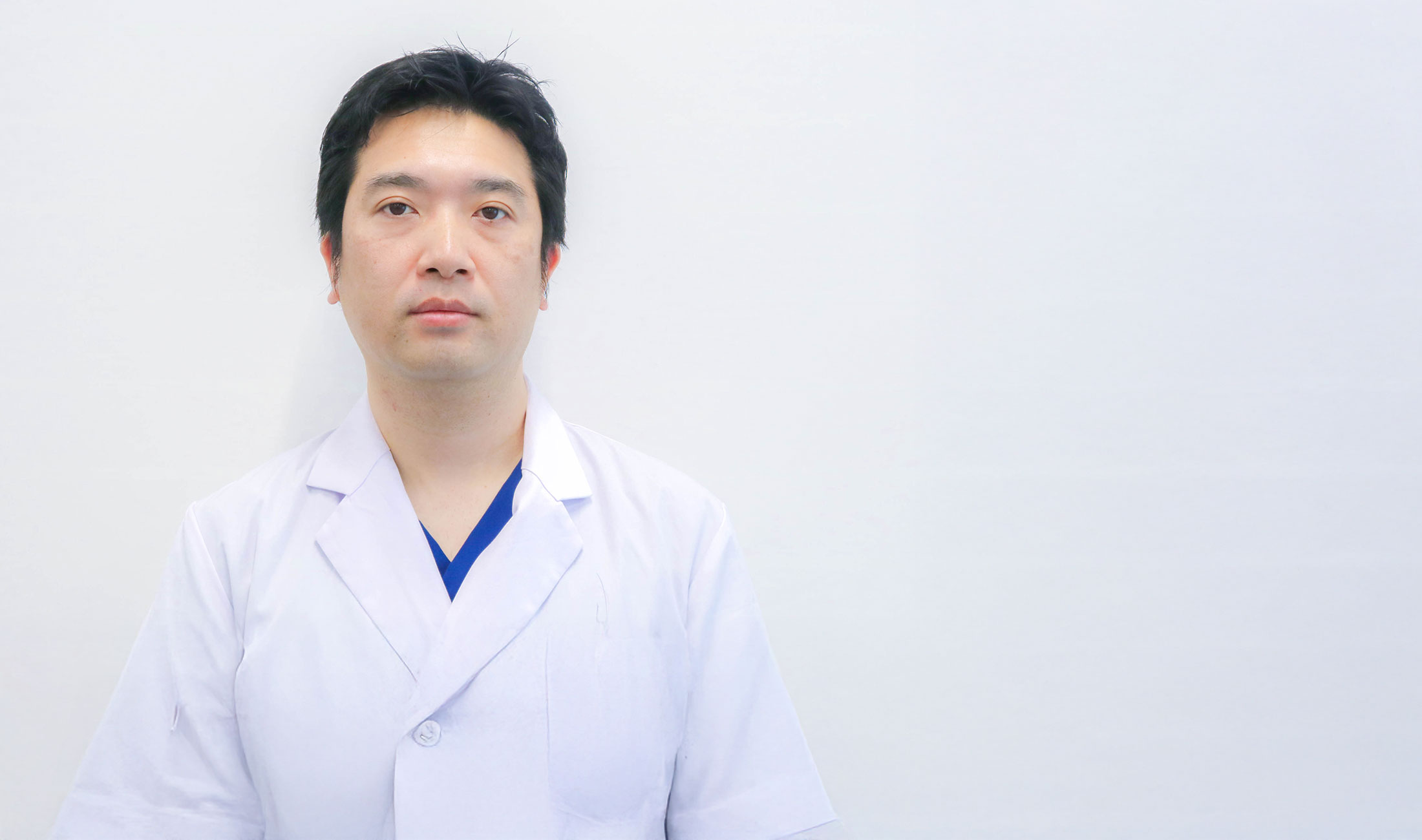
弁膜症を中心に幅広く心臓手術を行う
心臓血管外科では、診療責任者である畑先生のもと、私を含む4名の心臓血管外科専門医と2名の専攻医、合計7名で診療を行っています。実際の診療チームとしては6名が中心となり、週に最低5件、多い時には10件程度の手術を行っています。
当科の手術対象となる疾患は、主に弁膜症、狭心症、不整脈、心筋症などがあります。その中でも特に多いのが弁膜症の手術です。近年は予防医学が普及し、動脈硬化性疾患の患者数が減少傾向にあると感じています。動脈瘤などの症例数も減少しており、患者さんが意識的に予防や健康管理をされていることが影響しているのかもしれません。
根治性とのバランスを考慮し、低侵襲が基本方針
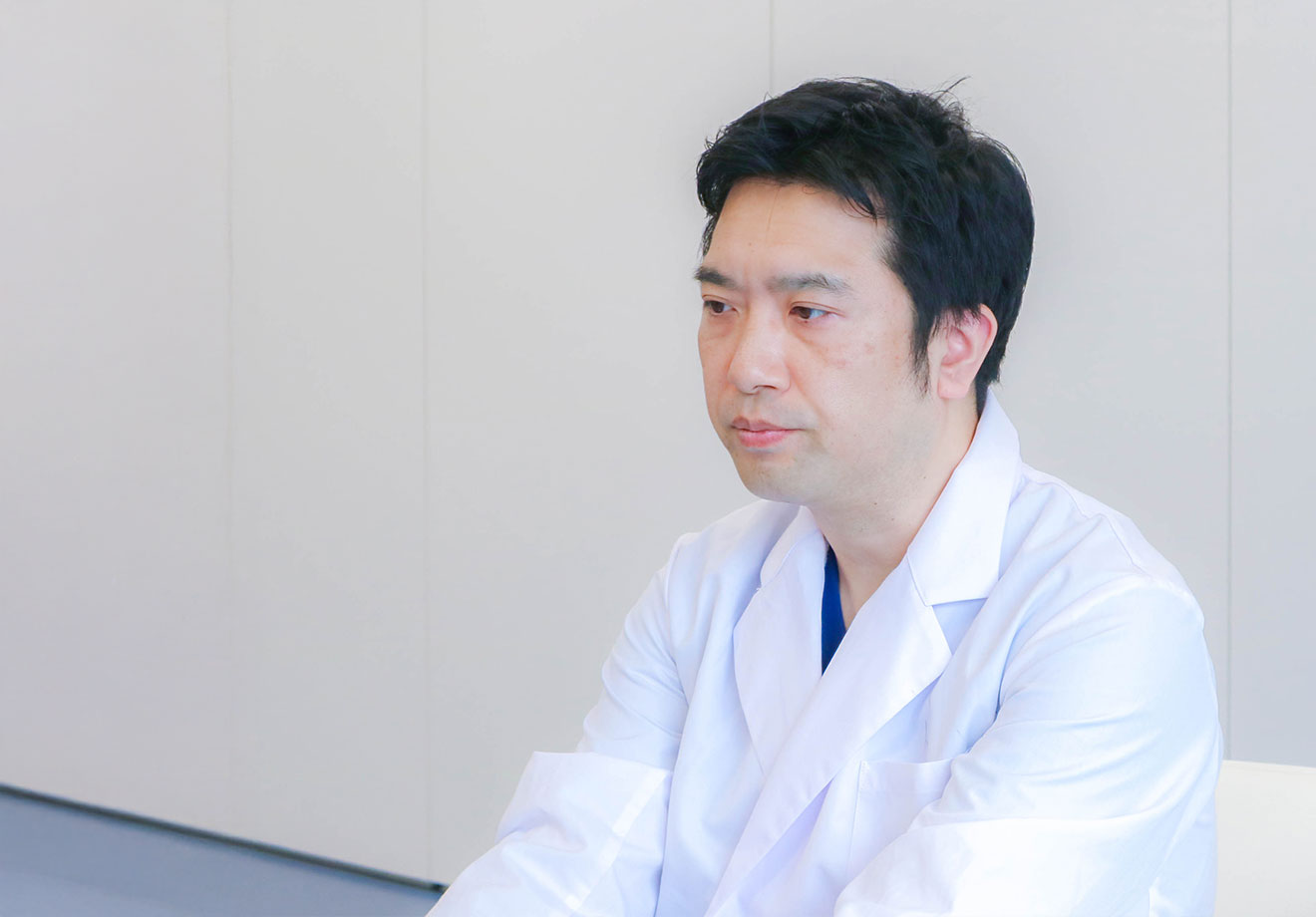
治療方針としては、患者さんの年齢にかかわらず、まず低侵襲治療が可能かどうかを検討しています。もちろん、低侵襲での治療が難しい場合や、根治性とのバランスがとれない場合には、より侵襲的な手術方法も選択肢に入れて検討します。ただし、高齢であったり基礎疾患が多かったりして、そうした手術に耐えられない可能性がある場合には、心臓内科との連携のもと、カテーテル治療などと組み合わせたハイブリッド治療を選ぶこともあります。
患者さんの病状、体力、生活背景に応じて、根治性と負担のバランスを常に意識しながら、柔軟かつ丁寧に治療方針を決定しています。
治療の選択肢の多さが強み
当院で行っている低侵襲治療の具体例としては、内視鏡手術やロボット支援手術(ダビンチ)があります。特に弁膜症の症例では、これらを組み合わせた「ミックス手術(MICS)」を基本としています。人工心肺の使用に大きな問題がない限り、多くの患者さんにこの方法を適用しており、一般的な施設では対応が難しい1弁、2弁だけでなく、3弁の同時手術や不整脈を合併した症例にも対応しています。
ただし、例えば冠動脈バイパスを同時に行う必要がある場合など、ミックス手術だけでは対応が難しいケースもあります。そのようなときは、まずカテーテル治療で冠動脈の病変を先に治療し、心臓手術と組み合わせて行うなど、柔軟な対応をとっています。治療の根治性と身体への負担のバランスを慎重に見極めたうえで、最適な治療方法を選択するのが当科の方針です。選択肢が多いこと自体が、当院の強みだと考えています。

手術と内科治療を中立に検討
弁膜症に関しては、TAVI(経カテーテル大動脈弁留置術)やマイトラクリップといったカテーテル治療も積極的に行っています。どの治療が適しているかは患者さんの年齢や全身状態、病変の程度によって異なるため、心臓内科と綿密にディスカッションした上で治療法を決定しています。実際に外科手術目的で紹介された患者さんであっても、内科的治療の方が適していると判断すれば、TAVIやマイトラクリップによる治療をご案内することもありますし、逆に内科から「TAVIだけでは不十分」と判断され、外科に紹介されるケースもあります。
私たちは、外科的手術とカテーテル治療の両方を同じテーブルで検討し、どちらかに偏ることなく、患者さんにとって最も負担の少ない治療を選択することを目指しています。両方をバランスよく組み合わせられる体制が整っていることは、当院の大きな強みです。
丁寧な説明とセカンドオピニオンにも対応
私の専門分野は、弁膜症と冠動脈疾患の外科治療です。とくに冠動脈疾患に関しては、冠動脈バイパス術(CABG)を中心に治療を行っており、虚血性心疾患に対するセカンドオピニオンも随時受け付けています。
近年では、冠動脈バイパス術においても、低侵襲な「ミックス手術(MICS)」が選択される機会が増えています。胸を大きく開かずに済むこの方法は、術後の回復も早く、患者さんの身体的負担を大きく軽減できます。当院でも、できる限りこの低侵襲な手法を取り入れた治療を提供しています。
私たちの役割は、必要な治療を的確に行うだけでなく、患者さんが納得し安心して治療を受けられるよう、正確な情報と選択肢を提示することにもあると考えています。もし治療に関して不安な点や他の意見を聞きたいと感じた場合は、ぜひセカンドオピニオンもご活用ください。
低侵襲なハイブリッド治療の発展を目指す
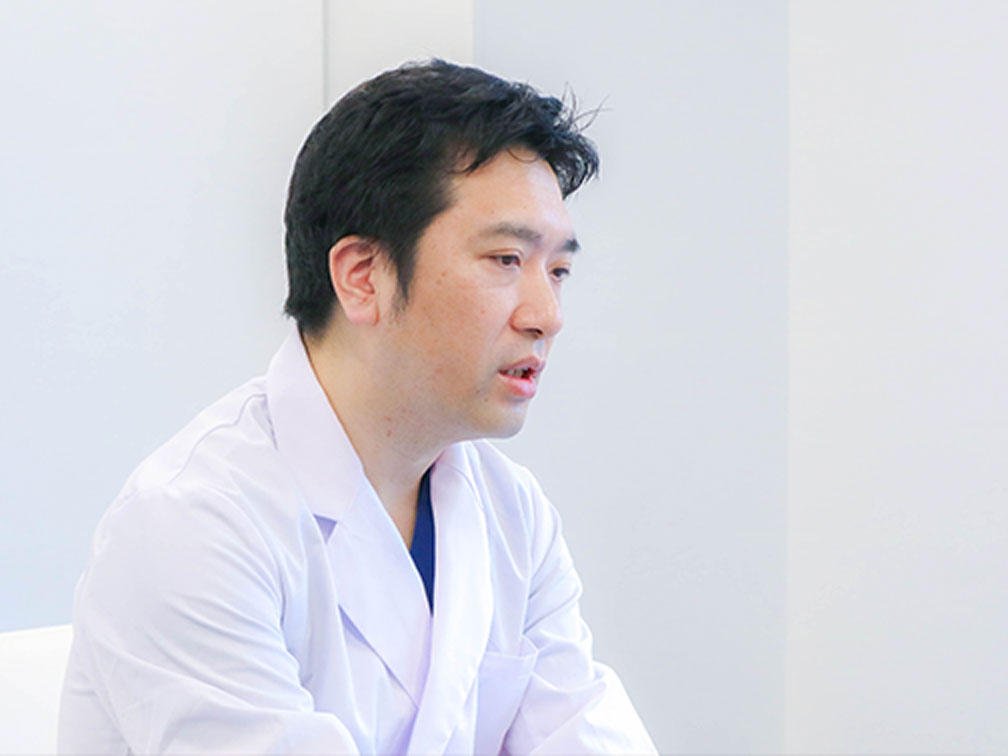
心臓血管外科領域における今後の先進医療について、私たちは常に技術革新とともに進化していく必要があると考えています。現在、外科的な進歩として注目しているのは、ロボット支援手術「ダビンチ」による治療のさらなる拡大です。
現時点では、ダビンチを用いたロボット手術は主に弁形成術や弁置換術に限られていますが、将来的には冠動脈バイパス術をはじめ、腫瘍性疾患や心房中隔欠損症(ASD)などの先天性心疾患にも適応が拡大される見込みです。保険診療としての枠組みが整えば、より多くの患者さんに対して低侵襲で精密な治療を提供できるようになると期待しています。そのためにも、常に新しい知識や技術を習得し、対応力を高めておくことが不可欠だと感じています。
また、低侵襲性という観点では、やはり内科的なカテーテル治療の優位性も無視できません。今後は、内科治療と外科治療の垣根を越えた「ハイブリッド治療」をいかに効果的に組み合わせ、患者さんにとって最も負担の少ない、かつ根治性の高い治療を提供できるかが大きな課題となっていくでしょう。
超高齢の患者さんにこそ、低侵襲手術の恩恵を
心臓血管外科の治療は、疾患によってはどうしても外科的な対応が避けられないケースがあります。たとえば、大動脈解離や心筋梗塞後の合併症などは、現時点ではカテーテル治療では対応が難しく、手術が必要です。
ただし、こうした手術を従来通りの胸を大きく開ける方法で行うだけでは、身体的な負担が大きく、高齢の患者さんにとってはメリットが少ないと感じています。だからこそ、85歳を超えるような超高齢の方にこそ、傷が小さく回復の早い低侵襲手術が有効だと考えています。
バイパス手術や一部の合併症については、患者さんの状態に応じてミックス手術(MICS)で対応することもあります。また、大動脈疾患などについては、カテーテル治療とのハイブリッド手術で、より安全に、できるだけ早期に自宅に戻れるよう支援しています。実際、当科に紹介される患者さんは「内科的にはもう難しい」というタイミングで来られることも多く、年齢やリスクが高い中で、どうすれば自宅復帰につなげられるかを常に考えながら治療を行っています。
地域の中核病院として、私たちは基本的に患者さんを「断らない」方針でいます。そのうえで、どう治療を工夫し、どうすれば85歳以上の方を家に返せるか。それが今後の大きな課題であり、鍵になるのはやはり低侵襲手術です。
就職をお考えの方へ

心臓血管外科は細分化が進み、すべてを網羅するのが難しい時代です。だからこそ「自分が何を専門にしたいのか」を早い段階で考え、その目標に向けて逆算したキャリアプランを立てることが大切だと感じます。
理想は、幅広い対応力を持ちつつも、明確な専門性を磨くこと。ロールモデルとなる医師を見つけ、実績や働き方を参考にしながら、自分の軸を持つと成長が加速します。
当院は症例数が豊富だからこそ、受け身では学びきれません。一例一例から学ぼうという意欲がある方にとって、大きな力をつけられる環境です。
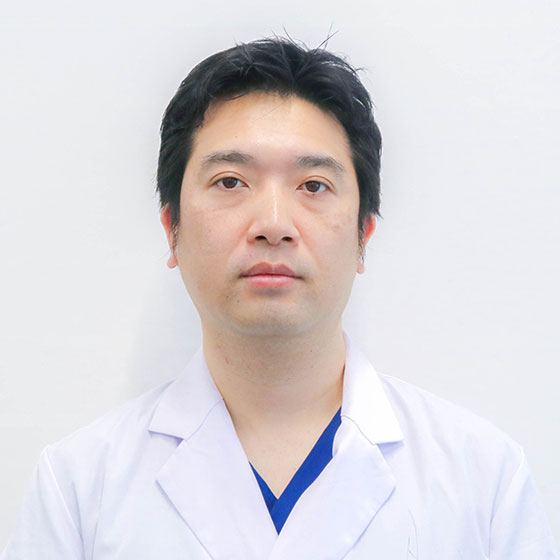
経歴
- 新潟県出身
- 2005年 東北大学卒業
- 2005-2010年 岩手県立中央病院
- 2019年より仙台厚生病院心臓血管外科